皆さんがお子様の教育資金を準備する際、真っ先に考えることは“どのように準備するのか?”という方法の話が多いのではないかと思います。例えば、銀行貯金・学資保険・NISAなど、どれが良いのか?ということです。しかし、一番最初に考えなくてはならないことは、“教育資金がいつ、いくら必要なのか”ということです。
“教育資金がいつ、いくら必要なのか”がわからない状態で、“どのように準備するのか?”という方法ばかり話しても、あまり効果的ではありません。
住まいの購入は、人生の大きなイベントのひとつ。希望する条件に沿った家を購入するために、多くの方が資金調達に奔走しています。
長く支払いが続く住宅ローンの負担を抑えるために、ご両親や祖父母から購入資金を援助してもらうのも、多くの方がとる調達方法のひとつです。ただし、身内だからといって気軽に援助を頼んでしまうと、あとから税金の支払いに苦しむことも。親子(または祖父母と孫)といえど、大きな金額を受け取った場合は贈与税がかかります。
ここでチェックしたいのが、両親、または祖父母から非課税で家づくりの資金援助が受けられる「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」。この制度をうまく使えば、贈与税の負担を抑えることができます。
目次
・非課税の最大金額1000万円、その利用条件をチェック!
・「質の高い住宅」を建てると、非課税枠が大きくなる!
・期間限定の特例制度なので、利用するタイミングに注意!
・最大非課税枠は2000万円!? 特例制度をさらに賢く使う
この「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」制度では、両親や祖父母から住宅購入資金の援助を受けた時、その資金の一定額については贈与税が非課税になります。
「資金の一定額っていくらなの?」と気になりますね。その最大の金額は「1000万円」。ただし、この制度を利用するにあたっては、いくつかの条件があります。
まず「直系卑属であること」。これは、贈与を受け取る人が子供か孫であることが条件という意味です。配偶者の父母は該当しないので、仮に妻の両親から夫が贈与を受け取る場合、この制度は適用されません。
また、受け取る人が18歳以上、その年の合計所得金額が2000万円以下であること(※1)も条件となります。
贈与を受け取ったら、速やかに家づくりをスタートしなければなりません。贈与を受けた年の翌年3月15日までには、その贈与分全額をあてた住宅を新築する必要があります。
※1 贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50平㎡未満の場合は1000万円以下)。
また、この制度を利用して建てる家についても、いくつかの条件があります。
新築の場合、最大「1000万円」という非課税枠は、「質の高い住宅」を対象としています。具体的には、耐震、省エネまたはバリアフリー仕様となっていること(※2)。この条件に該当しない一般的な住宅は、非課税枠が500万円となります。
また、完成後はその家に住むことも条件とされています。具体的には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家に住む見込みがあることが申請時での条件です。翌年12月31日までに実際に居住していないと、適用が受けられなくなるので要注意です。
※2 ①断熱性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上もしくは免震建物等
③高齢者等配慮対策等級3以上
①~③のいずれかに該当することが条件
上記のほか、この制度を利用するにあたって、いくつか注意したい点があります。
まず、この「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の特例」は、令和4年4月1日~令和5年12月31日までの期間限定の制度です。家の完成が翌年だとしても、令和5年の年末までには贈与を受けておく必要があります。また、平成21年から令和3年分までの贈与税の申告において、「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けた場合、この制度は使えなくなるので注意しましょう。
贈与を受けた人がこの住宅を所有しない場合も、この特例の適用を受けることはできません。また、住宅を購入する場合、親族などからその住宅を取得する場合も適用されません。
この「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を、さらに賢く使いこなすコツがあります。
上記でご説明したように、この制度は「直系卑属であること」が条件。ただし、ご夫婦の場合、夫婦がそれぞれの親から贈与を受けることが可能です。つまり、夫婦がそれぞれの両親から1000万円の贈与を受けた場合、最大2000万円が非課税となります。ただし、購入する家を共有名義にする必要があるので注意しましょう。
また、この制度のほかにも、毎年110万円までの贈与であれば、非課税枠となります。この非課税枠と「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」をダブルで適用することもできます。
♢
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を利用する場合のさらに細かい条件や申請手続きについては、国税庁のHP(※3)で説明されているので、参照してください。
特に、申請のタイミングが遅れるとこの特例を利用できなくなるケースもあるので注意が必要です。
「こんな家に住みたい」「素敵なライフスタイルを実現したい」という理想をあきらめないためにも、資産調達は家づくりの大切なポイント。ご家族ともじっくり相談しながら、納得のいく家づくりを実現してください。
※3 国税庁HP(https://www.nta.go.jp/)
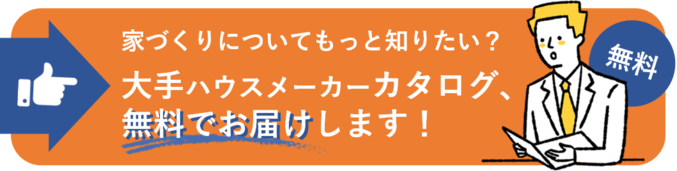
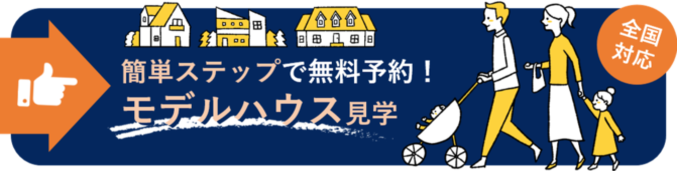
皆さんがお子様の教育資金を準備する際、真っ先に考えることは“どのように準備するのか?”という方法の話が多いのではないかと思います。例えば、銀行貯金・学資保険・NISAなど、どれが良いのか?ということです。しかし、一番最初に考えなくてはならないことは、“教育資金がいつ、いくら必要なのか”ということです。
“教育資金がいつ、いくら必要なのか”がわからない状態で、“どのように準備するのか?”という方法ばかり話しても、あまり効果的ではありません。
まず、教育資金がいくらかかるのか考えていきましょう。 よく、子供一人育てるのに1,000万円~1,500万円かかるとい言われますが、これは本当でしょうか?
文部科学省「平成26年度 子供の学習費の合計(学校教育費、学校給食費、学校外活動費(塾、習い事))調査」によると、下記のようになっています。

例えば、幼稚園(私立)→小学校~高校(公立)→大学(私立文系)という進路を進む場合、1,000万円を超えます。この文部科学省のデータは平均値、目安なので、習い事や塾の費用が多い家庭や進路先が地元を離れ下宿生活になったり、医科・歯科大学を希望すれば、もっと教育資金は必要になります。
1,000万円~1,500万円かかるといわれるのはあながち間違いでないようです。
1,000万円~1,500万円と聞くと、多くの方が『ショックを受けたり、そんなに用意するのは無理だよ』といった感じになると思います。
しかし、ご安心ください。いくらかかるかより、大切なのはいつ必要なのかです。年間にかかる学習費で計算してみましょう。

これを月間で考えると、下記のようになります。

いかがでしょうか?まとまった資金だと『無理だ、大変だ』という感じになります。しかし、月々で考えると『どうやって支出を減らすか、どのように準備をするか』といったように、どのようにやりくりをすれば資金を準備出来るか、と考えることが出来るのではないでしょうか。
例えば、幼稚園(私立)→小学校~高校(公立)→大学(私立文系)という進路の場合で考えてみましょう。月々の費用で考えると、大学までの費用は5万円/月前後ですが、大学では倍の約10万円/月がかかります。
また、県外の大学に進学する場合があることも考えると、上記学習費に加えて、自宅から通う場合でも通学定期代が、一人暮らしの場合には下宿費用などもかかることになります。
高校までの学習費5万円/月は月々の収入で頑張ってやりくりすることは可能だと思います。しかし、大学の学習費+αを月々の収入でやりくりすることは、余程やりくり上手でなければ難しいはずです。
この不足する可能性がある費用の準備方法としては、『児童手当を銀行積立する』ことが良いと思います。
児童手当は下記のようになっています。
| 0歳~3歳 | 15,000円 |
| 3歳~小学生 | 10,000円 (第三子以降:15,000円) |
| 中学生 | 10,000円 |
これを計算すると、15,000円×12か月×3年=54万円、10,000円×12か月×12年=144万円。合計すると198万円の資金になります。この198万円を、大学の学習費に直すと(198万円÷4年÷12か月)4.1万円/月の補填になると考えられます。
ところで、なぜ“銀行積立”なのかというと、その理由は以下になります。
まずは、使い勝手の良い児童手当を銀行で積立して、余裕があれば別の方法である学資保険やNISAにチャレンジするのが良いと思います。
土地選び、建物、外構など、こだわりをもてばどうしても予算オーバーになりがちです。 しかし、ハウスメーカーや工務店などから紹介される予算アップ案は、自分の親・祖父母からの非課税枠を使った贈与の話であることが多いのです。ですが、親・祖父母側から話をいただけるならまだしも、自分から援助の話を持ちかけるのは、抵抗があると思います。 今回は、自分でできる予算アップの方法をご紹介したいと思います。
住宅購入後に保険の見直しをするといいよ!とアドバイスをもらい、見直しを考える方は多いと思います。理由は団体信用生命保険に加入することで、ローン契約者に万が一のことがあっても、保険会社がローンを代わりに払ってくれるので、残された家族は住宅ローンの返済で困ることはなくなります。住む家は確保できるので、住宅費分の保険を減らすことができます。
しかし、実際は住居費分の保険を見直してもそれほど予算アップに効果は大きくありません。
一番効果を実感できる方は、貯蓄型の保険(学資保険、個人年金保険)に入っている方です。
この部分を個人型確定拠出年金iDeCoや積立NISAなどを上手く活用すると、3分の2・2分の1の掛け金で目標金額を準備できる可能性もあるのです。
予算アップの効果は貯蓄型保険ほどではありませんが、例えば死亡保険なら、遺族年金を考慮する、たばこ、BMIなどの保険割引を使う。医療保険、がん保険なら、高額療養費や会社の付加給付を考慮するなどがあります。
具体的な保険の見直し、貯蓄、運用の見直しの方法の詳細は省きますが、仮に月10,000円の保険料を節約できれば、 10,000円×12か月×35年間(ローン期間)=420万円の予算を作り出すことができます。
保険料を10,000円以上支払っている方は、見直しを検討して、予算アップしてみてください。ただし、見直しに行って営業マンの話を聞いて逆に高くなることがないよう気をつけてください。
皆さんは自動車の維持費って計算したことありますか?
自動車税、重量税、自賠責保険、任意自動車保険料、ガソリン代、車検代、オイル、タイヤ交換、洗車代、駐車場代、ローンで購入している人は月々のローン代。たくさんの項目があります。
諸々の費用(本体のローン除く)を軽自動車、5ナンバー、3ナンバーで分けると、月々に下記くらいの金額がかかります。
| 軽自動車 | 25,000~30,000円/月 |
| 5ナンバー | 30,000~35,000円/月 |
| 3ナンバー | 35,000~40,000円/月 |
地方の方で車での移動手段が必須の方、車が趣味の方などは無理して削る必要はありません。しかし、バス・電車などの公共交通機関が充実している方で、基本土日しか運転しない方など、ライフスタイルの変化が可能であれば見直し検討余地ありです。
レンタカー・カーシェア・タクシーなどの新しいライフスタイルに変えることで、仮に月10,000円を節約できれば、10,000円×12ヶ月×35年(ローン期間)=420万円の予算アップの可能性があります。
ただし、所有者から、レンタカー・カーシェア・タクシーへのライフスタイル変更は、保険とは違うので、実生活でのメリット、デメリットも良く考えて見直ししてください。
今や1人1台が当たり前の携帯電話(スマートフォン)に加え、タブレットを持ち、自宅でのインターネット回線・固定電話など様々な通信費がかかっています。この通信費、気づかないうちに家族で2万円、3万円と多くなっていませんか?夫婦の携帯代が2万円、家のインターネット、固定電話で1万円という家庭があります。
見直しのポイントとしては、下記の3点から考えてみると良いと思います。
現状を把握した上で、今使用しているキャリア(ドコモ、ソフトバンク、auなど)で料金プランの見直し、Wi-Fi・ルーターの設置など、どうしたら安くなるかを店員さんに聞くと色々アドバイスがもらえるはずです。ただし、現在の通信費よりも結果的に高くならないように気をつけてください。もし、それでも安くならなければ、格安SIMなどのキャリア変更も検討すると良いと思います。
仮に夫婦で月2万円の通信費が1万円になれば、10,000円/月×12ヶ月×35年=420万円の節約≒予算アップに繋がります。
以上のように、月2万円の保険・車・通信の費用が1万円になれば、30,000円/月の家計改善となり、30,000円/月(保険・車・通信、各10,000円)×12ヶ月×35年=1,260万の節約≒予算アップに繋がります。
住宅購入後の家計改善より、住宅購入前に家計の見直しをして、ぜひ予算で妥協しない家づくりを目指して下さい。